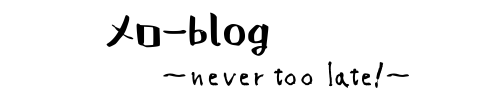とある・・・
地域ケア会議での一幕。

さん
利用者様が、お風呂に行けないんです。どうしたらいいでしょうか?
<地域ケア会議とは?>
「地域の高齢者の自立した生活を支援するため、その支援方法を検討するための会議のこと」です。また、地域の課題を把握し、解決することも目的となっています。会議には、地域の医療・介護に係る専門職などが参加します。
今回の会議の事例担当者である
ケアマネジャー(介護支援専門員)さん
からの質問。
詳しくお聞きすると、

さん
担当している利用者様の車いすがドアに接触してしまい、浴室がある脱衣所に移動することが出来ないんです。
ということでした。
実は、この利用者様。
「入浴は施設のデイサービスで行い、
自宅では入浴しない。」
このような計画で
介護サービスを
スタートされていました。
しかし、
デイサービスに行くうちに、

お風呂が気持ちいい。シャワーだけでもいいから、自宅でもお風呂に入りたい。
そんな気持ちが芽生えたとのこと。
前向きで意欲的な心の変化!
素晴らし~(*^^*)
この気持ちを大切にしたい。
なんとか希望を叶えたい。
会議出席者の方々も力が入ります。
「車いすがドアを通らない!」
築年数が経過した建物において、
今回のような事例は少なくありません。
「地域ケア会議」では、
通常の対応で解決が難しい事例が
検討事項として挙がってきます。
そんな時、
参加している専門家の
『裏技的なひらめき💡』が
解決の糸口になります。
そこで今回は、
「車いすがドアを通らない時の対策」
について、
地域ケア会議であがった意見を参考に
その『裏技!』を
ご紹介したいと思います。
最後まで読んでいただけたら
嬉しいです。
- 車椅子がドアを通らず困っている方。
- 車いす生活となっても、住み慣れた自宅で生活したいと思っている方。
- 在宅医療や介護に携わる専門職の方。
1.通常の対応

今回のような場合、
通常どのように
対応するのでしょうか?
まず思い浮かぶのは、
「ドアの幅に合わせた車いすの選択」
今回はケアマネジャーさんが対応。
色々と検討された結果、
「ドアを通る車いすがなかった」
とのこと。
次に浮かぶのは、「住宅の改修」
こちらもケアマネジャーさんが対応。
※介護保険では、「住宅改修費」として20万円までの住宅改修費用に対し補助される制度があります。利用者のご負担は、そのうち1~3割となります。
しかし、当初の計画では
デイサービスでの入浴を想定。
そのため、
「住宅改修費」については、
利用者様と相談し
スロープやトイレなどに使用。
「補助される費用が残っていない」
とのこと。
地域ケア会議の参加者も
頭を抱えます。
ふとちょっとした「裏技」が
私の頭に浮かびました。
着目したのは、
「ドア」と「車いすのハンドリム」
では、
その裏技について
ご紹介したいと思います。
2.裏技①:ドアを取り外す
-1024x683.png)
今回の利用者様のお宅。
脱衣所入り口のドアは、
「開き戸」とのこと。
そのため、
ドアを開いた時にその「厚み」が影響。
開口幅がドアの「厚み」分マイナスとなり、
開口部が狭くなっていました。

これにより、
実際の開口部の幅より
小さい車いすでも、
通る時にはドアに接触してしまう。
このような現象が、
起こってしまったのです。
そこで裏技!

ドアが開口幅を狭くしているのであれば、思い切ってそのドア自体を取り外してはどうでしょうか。
ドアを取り外す!?
一見、荒業のように感じます。
しかし、
そうすることで
間口部を狭くしていた
「ドアの厚み」がなくなり、
実際の開口幅を確保できます。
開口部の幅より
小さい車椅子であれば、
通ることが出来るようになるのです。
ずいぶん昔ではありますが、
以前、訪問リハビリを行っていた時に
一度だけドアを取り外して
対応した経験がありました。
会議出席者の方々も頷きます。
ドアの取り外しは、
それほど難しくはありません。
ケアマネジャーさんや
サービス担当者の方が協力すれば
出来ない作業ではありません。
ドアを外した後は、
突っ張り棒などを利用した
簡易的なカーテンを取り付ければ 、
目隠しや空調などへの配慮も可能です。
少し荒療治的ではありますが、
やってみる価値は
あるのではないでしょうか。
3.裏技②:ハンドリムを取り外す

もう一つは
車いす自体に対応する方法です。
今回の利用者様がお使いの車いす。
いわゆる「標準型車いす」
利用者様ご自身で駆動するタイプです。
両方のタイヤの外側に設置されている
「ハンドリム」という部分を使って
駆動します。
しかし、
この「ハンドリム」
車いすの一番外側に設置され、
右と左のハンドリムまでの幅が
車いす全体の幅となります。

そのため、
ドアに限らず
廊下や廊下の曲がり角など
「ハンドリム」が接触してしまう例は
少なからずあります。
今回の事例も
ハンドリムが接触している模様。
そこで裏技のご提案!

思い切って、車椅子の「ハンドリム」を取り外してみたらどうでしょうか。

さん
「ハンドリム」がなくなったら、どうやって車椅子をこぐんですか?
ケアマネジャーさんからの質問。
ハンドリムがなくなれば、
車いすを駆動させる部分が
なくなります。
しかし、
車いすにはタイヤがあります。
自走式の車いすでは、
乗車している人の手が届く位置に
タイヤが設置されています。
そのタイヤを手で押して
駆動してはどうでしょう。
ただ、注意点もあります。
車いすのタイヤは元々、
手でこぐように作られていません。
そのため、
駆動する際に手を傷つけてしまう
可能性があります。
また、
車椅子を屋内と屋外で
併用される方は、
帰宅した際に
十分に清掃されたとしても
手の清潔が保たれない
可能性があります。
その他にも、
使用される方の状況においては
様々な注意が必要でしょう。
しかし今回は、
車いすでドアを通り抜け
自宅のお風呂に入ることが目的。
様々な注意点はあるものの、
その注意点に何らかの対策を講じて
挑戦する価値はあるかもしれません。
4.その他:車いす選定の見直し

今回の事例では、
「標準型車いす」が
選定されていました。
しかし、
市販されている車いすには、
さまざまな種類があります。
「6輪の車いす」など
今回のような
狭い空間で使用することを
想定して作られた車いすもあります。

出典:日進医療器株式会社 「車いす・福祉用具総合カタログ Vol.18」デジタルブック
また、
介護保険によるレンタル品でも、
カスタマイズを加えることが
可能な場合もあります。
そのため、
利用者様の身体の状態に
出来るだけ合わせた
車いすを提案して下さる
業者の方が増えています。
再度、
車いすの種類を見直すことも
検討してもいいかもしれません。
5.まとめ

今回は「車いすがドアを通らない」
その場合の「裏技!」について、
「ドアを取り外す」
「ハンドリムを取り外す」
この二つの方法を
ご紹介させていただきました。
また、
「車いす選定の見直し」も
提案させていただきました。
ドアにとどまらず、
室内や廊下など
車いすでの移動が妨げられる場面は
少なくありません。
そんな時、
ケアマネジャーさんや
私のようなリハビリの担当者など、
身近にいる専門家に
相談してみてください。
きっと専門的な知識と経験から
解決策を導き出してくれる
と思います。
また、
すぐに解決できない場合でも
「地域ケア会議」のような
様々な専門家が集う会議もあります。
みんなの力を集めれば
解決できない事はありません。
ふと頭をよぎる裏技的アイデアが、
解決の糸口になることもあります。
利用者様の前向きな気持ち。
これに応え安心していただくためにも、
私たち専門家の知恵を結集し
諦めることなく対応していきたい。
そんな風に思っています。
最後まで読んでいただき
ありがとうございました。